起業家人材育成に力を入れてきた近畿大学では、2025年までに大学発ベンチャー企業100社を創出することを目指し、学内での起業プログラム整備やビジコン開催などあらゆる取り組みを行い、その結果、目標よりも1年10ヶ月早く近畿大学発ベンチャーを100社輩出することができました。(※2025年3月時点で134社)
これは近畿大学の学生に対する手厚い創業支援を、迅速に整備し続けたことが要因ではないかと考えられます。
その秘訣を、近畿大学で起業支援の司令塔として取り組まれている経営戦略本部起業・関連会社支援室の事務長高木様に伺いながら、今回2024年12月に開催された「近大ビジコン2024」の取り組みについてもお聞きしようと思います。
近畿大学における具体的な起業支援については過去の記事をご覧ください。
・近畿大学における起業支援について(2024年1月25日公開)
https://madeinlocal.jp/category/localist/027
大学発ベンチャー100社輩出の背景
1-1. 近畿大学が2025年までに大学発ベンチャー100社を輩出する目標を、1年10ヶ月も早く達成されていました。起業・関連会社支援室として上手くいった秘訣は何だとお考えでしょうか?

(※画像の企業数は令和5年12月11日時点でのデータです)
やはり、起業支援プログラムを幅広い層に提供したことによって、参加者の分母を確保できたことが要因だと考えています。
本学では、学生のレベルに合わせて①起業憧れ層 / ②起業予備層 / ③起業準備層の3段階に分けて、きめ細やかなプログラムを実施し、起業に必要な要素や情報を得る方法を提供してまいりました。起業に対しての抵抗をなくし、学生の間に沢山チャレンジして欲しいという想いがあるので、参加しやすい環境づくりと、次の段階にスムーズに移行できるよう設計しています。
起業憧れ層に対しては、各種イベント・セミナーを開催し、学内の若手起業家や、学外からも様々な知見を持つ方をお呼びして、価値観を広げられるようにしています。
まず、起業や事業立ち上げは最初から成功することはほとんどない世界で、失敗することが前提であることを知ってもらいます。学生の起業経験は将来的に就職を選ぶ際にもビジネスの世界での考え方・行動の仕方・人脈にもつながり、とても貴重な経験を得られるイメージがここで湧くでしょう。
起業予備層については社会起業家育成プログラム「DiG」・起業体験講座「KINDAI STARTUP ACADEMY」・新規事業開発プログラム「Lean LaunchPad」等、実際に行動してみて事業立ち上げや起業を体感してもらいます。PDCAを高速で回していくためには、早く行動・早く失敗経験を積み、それを早く振り返ることだと考えています。
そして、起業準備層については「法人登記・開業支援プログラム」を提供し、実際にビジネスを法人として進めていくことを前提にあらゆるメンターや専門家の指導を経て、プランが認められたら法人登記費用を提供しています。
現代は、不確実性の高い世の中だからこそ、起業という選択肢を取る若者も増えましたし、学生時代の起業経験を基に就職し、ビジネスの世界で活躍している方も沢山増えました。
だからこそ、「少し興味はあるけれど……」という学生には1人でも多くチャレンジして欲しいと本気で思っています。
<もっと詳しく>KINCUBAについて・SUPPORT CONTENTS
https://www.kindai.ac.jp/kincuba/about/
学外の広報としては、主にオープンキャンパス時に、KINCUBA Basecampの存在を全面に押し出しています。
西門の前にあるので、東大阪キャンパスに来場する学生は必ず目の前を通ることになります。
例年、来場者数は増加しており2024年の本学のオープンキャンパスの総来場者数は46,027人に対し、KINCUBA Basecampの来場者は5,808人であったため約8人に1人が訪れていることになります。
また、これは起業・関連会社支援室の取り組みとは別件になりますが、2025年度入試から経済学部で起業志望の高校生を対象とした総合型選抜が導入されることになりました。
それによって、経済学部棟のエレベーターにもKINCUBAのチラシが貼っていますし、「近大=起業支援」というイメージが着実に学生や、志願者にも伝わっていると実感しています。
1-2. 一旦、目標である100社の設立を達成されましたが、今後はどのような目標を掲げて、大学として支援を進めていく予定でしょうか?

起業気運を高めるため、研究者・学生を対象の支援をさらに拡充し、起業に強い大学というブランディングを確立していきたいです。まずは、西日本の私立大学で1番多くの大学発ベンチャーを創出する学校を目指したいと思っています。
また、2021年10月から、学生飲食店起業支援プロジェクト「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」を実施し、東大阪キャンパス内で在学生がラーメン店を経営しています。このように、飲食ビジネスを中心に、学生によりリアルな経営を体感してもらう場所・環境を作っていきたいと考えています。
起業といえば、頭脳明晰な人が資金調達を行って立ち上げるITベンチャーやAIといったイメージが強いかもしれませんが、本学が東大阪という中小企業の町・ものづくりの町にいるからこそ、「商売」からお金を得る難しさ・やりがいを学んで欲しいと思っています。
本プログラムでは、すごい企業を作ってほしいというよりも、事業立ち上げ・商売を通して、自分で考える力を養い、自分で判断するという経験を若いうちから得てもらうことが将来のキャリア選択に大いに役立つと考えています。
近大ビジコンについて
2-1.2019年から近畿大学でビジコンが開催されていると伺ったのですが、年々規模を増して開催されているように思われます。今一度、近大ビジコンのこれまでの歴史を教えていただけますでしょうか。

2021年9月に経営戦略本部に起業・関連会社支援室が新設される前から起業支援の取組やビジコンのような催しを行っておりましたが、近大ビジコンという名称で本格的に開始したのは2021年からです。
近大ビジコンは、「グランプリ部門」(起業済または起業に向けた具体的なビジネスプランを有する学生の部門)と、「チャレンジ部門」(起業前かつアイディア段階のビジネスプランを有する学生の部門)に分かれており、それぞれの観点で広く良い事業アイディアを募集してきました。
2-2.今まではどのような方が近大ビジコンに携わっていたのでしょうか。また、このビジコンで表彰された方にはコンテスト後にどのように大学としては関わっているのでしょうか?

近大OB・OGの経営者を始め、経営者の方・銀行をはじめとする金融機関の方・ベンチャーキャピタル(VC)の方等を審査員として招いておりました。また、エントリーからファイナリスト選定のフェーズにおいても、起業経験のある方々に支援いただき、選定しております。ビジコンで受賞するか否かに関わらず、事業に挑戦する起業家の支援は継続して行っています。
今回の2024年12月に開催した近大ビジコンでは、前吉本興業ホールディングス株式会社代表取締役会長の大﨑洋さんをはじめ、錚々たる方々に審査員を務めていただいたこともあり、過去最大で注目を集める大会となりました。参加学生には普段触れ合う機会の少ないベテラン経営者の方々から勇気をもらえるフィードバックを通じて、より自分のアイディアと自分自身を磨いて成長してほしいと思います。
2-3.今回の2024年大会はグランプリ部門の最優秀賞が200万円+「KANSAI STUDENTS PITCH Grand Prix2025」出場権獲得とかなり豪華であるようにお見受けします。それだけレベルが高いコンテストだと思いますが、前年とはどのような点がアップデートされたのでしょうか?

大きくアップデートした点としては、今年からは近畿大学校友会が後援となったことで、多くの賞金をご用意いただけることになりました。そういったOB・OGからも近畿大学発ベンチャーを育てていく取り組みは非常に期待されているものと実感しています。
今後も、学内の起業支援の取り組みが厚さを増していくことによって、これらの大会での賞金や副賞・参加することに対してのモチベーションアップになる要素がさらに増えていくと思います。
これにより、学内だけでなく学外からも注目されるようなビジコンを毎年開催できると嬉しく思いますし、昨年受賞を逃した学生も「来年こそは最優秀賞を獲るぞ」と張り切っているので、そういった人たちのためにも毎年アップデートし続けなければならないと思っています。
まとめ
3-1.今後、ビジコンだけでなくあらゆるプログラムを提供している近畿大学では、どのような支援及び起業支援に対する広報活動を行っていくご予定でしょうか?

これまで以上に研究者・学生に対する支援を継続するとともに、プログラムの刷新なども視野に入れ、本学の起業支援体制を拡充していきたいと考えています。具体的には、本学が有する研究シーズを商用化したいと考える学生や、ゼミ生に指導していく中で教員側にも起業・ビジネスの観点からアシストしてもらえるようにサポートを行っています。
我々としては、少しの挑戦心やアイディアも無駄にしないように、学生の可能性を広げていきたいと考えています。
さいごに

2024年12月11日に開催された近大ビジコンは、過去最大規模の大会となりました。
起業済または起業に向けた具体的なビジネスプランを有する学生の部門「グランプリ部門」と起業前かつアイディア段階のビジネスプランを有する学生の部門「チャレンジ部門」の2部門で構成されており、グランプリ部門では最優秀賞は賞金200万円+KANSAI STUDENTS PITCH Grand Prix2025 出場権・優秀賞は賞金50万円。
チャレンジ部門においても最優秀賞は賞金50万円+事業化サポートが受けられます。
(その他、オーディエンス賞他、10社の協賛賞が用意されました。)
グランプリ部門 最優秀賞「株式会社2ndStarの越智 健心さん」は、家業が建設業であるため、道路やトンネルといったインフラのメンテナンス不足によって日本国内において事故が多発していることに危機意識を持ったそうです。
ソフト・ハードの両面から真の維持管理DXを実現するため、データ収集・報告等の事務作業簡略化及び、AIを活用した工法の分析を導く「2ndStar」をリリースされました。現在は鉄道業界を中心に拡大し、後に他業界にも展開予定のようです。
グランプリ部門優秀賞「ウェルヘルス株式会社の土井 久生馬さん」は、白血病で2年前に他界した自身の弟から「病気と闘うことの壮絶さ」を学んだ経験を基に、「痛い・辛い・しんどい」で治療する人を減らしたいと考え、ビジョン「健康社会の実装」/ミッション「治療から要望がベースの世界へと成長させる」を掲げ、2023年にウェルヘルス株式会社を設立されました。
生活習慣病を予防するために、労災保険二次健康診断の導入支援を行っておられます。労災を発生してからではなく、健康診断でリスク把握できた人に提供する日本初のビジネスモデルであり、今後5年で毎年2000万人の健康診断のデータを蓄積し、ビックデータを駆使し、テクノロジーで健康を創るという壮大な構想をプレゼンされました。
チャレンジ部門 最優秀賞「濱本 智義さん」は、自身の「とりあえず、大学に行きなさい。」と母親や学校に言われたことを鵜呑みにしたものの、自分のやりたいことが分からなくなって後悔したことと、大学時代に様々な環境にチャレンジした経験から、「可能性は環境と行動でできる。」と気づき、子供の選択肢を広げるオンライン英会話×IT教室 『Another School』を企画されました。
リベラルアーツと探究の二軸で教育を行うことで、興味を広げ実行力を高められるので「自分の可能性を広げられる」子どもを増やしたいと考えられています。
KINDAIビジコン2024の出場者情報や当日の様子はYoutubeでも全編ご確認いただけます。
全ての発表が非常にレベルの高い内容でしたので、是非ご覧ください!
KINDAI BUSINESS CONTEST 2024
https://www.kindai.ac.jp/kincuba/biz-con/2024/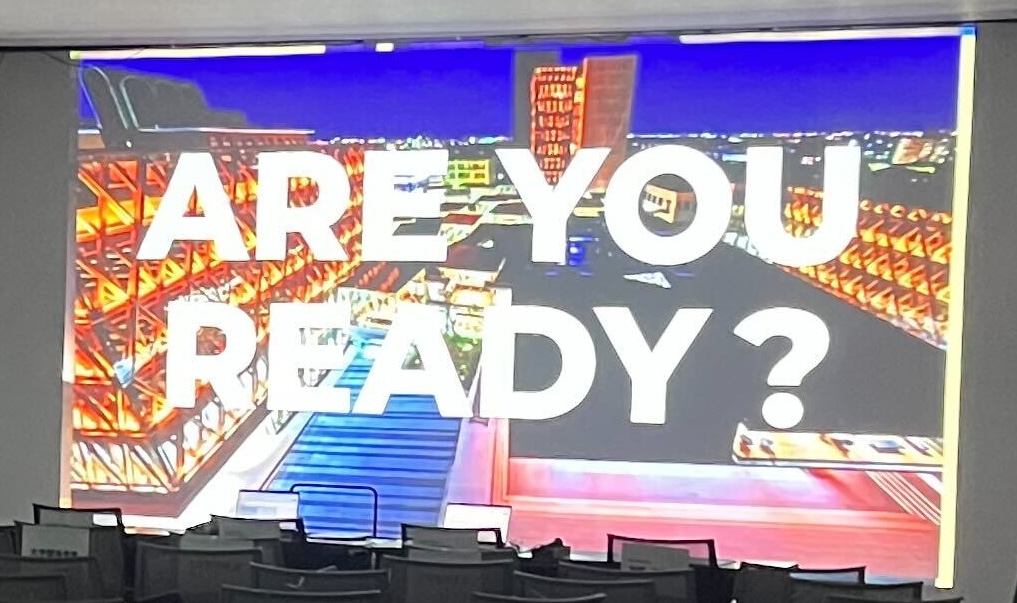
また、後日開催された「KINCUBAメンター交流会」の挨拶にて、経営戦略本部長の世耕石弘さんからは「近大マグロの次は、起業です!」というお言葉もあり、「起業支援」というジャンルが学内で最も注力されている分野の一つであると感じました。
近畿大学は志願者数で全国トップを誇る人気大学であり、その大学が全力で起業を支援しているのは、社会に出る前にやはり起業・事業立ち上げ経験を学生に体感してもらうことによって、これからの不確実性の高い世界を自由に自分らしく生き抜いていける力を身につけて欲しいという親心のようなものを感じました。
そのためには、大学として一定数目標を定める必要があり、創立100年までに100社の近畿大学発ベンチャーを創出するという、かなり短期間で難しい目標設定をされたのだと思います。しかし、面白い大学としてどんなことをしてくるのか、その大学に通う学生はどのような面白い人材なのかを世の中は常に注目しています。
近畿大学発ベンチャー100社を突破した今、次に近大はどのような一手で私たちをワクワクさせてくれるのか目が離せないですね。
関連記事
近畿大学における起業支援について
https://madeinlocal.jp/category/localist/027
大学名:近畿大学
所在地:大阪府東大阪市小若江3丁目4−1
設立年:1949年
名 前:高木 純平 (起業・関連会社支援室 事務長)
リンク:https://www.kindai.ac.jp/kincuba/

エリアから探す
北海道・東北
関東
中部・北陸
近畿
中国・四国
九州・沖縄
お問い合わせ
掲載依頼・取材依頼・Made In Localシリーズおよび地域を代表する企業100選についてのお問い合わせ等、承っております。まずはお気軽にご相談ください。
会社概要
Made In Localは、株式会社IOBIが運営する地方創生メディアです。弊社では現在、事業拡大につき、新卒・中途ともに積極的に採用活動を行っております。 ご興味のある方はぜひご一読ください。
Made In Localは地方創生メディアの運営を通して地域の産業振興や地域間格差の是正に取り組んでおり、「産業と技術革新の基盤をつくろう」・「人や国の不平等をなくそう」・「住み続けられるまちづくりを」の3つのSDGsのターゲットの実現を目指しています。































































