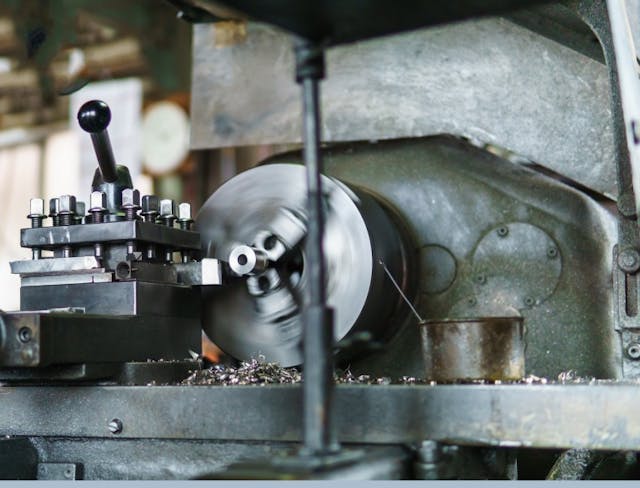企業のこれまでとこれから
御社の創業から現在に至るまでの歴史について、転換点となった出来事を含めて教えてください。
1957年、鹿児島市で現社長の父、永田次雄が創業した国内初のCROです。91年から臨床薬理試験受託、99年から臨床試験受託を開始、2000年代に入り海外展開と経鼻投与製剤基盤技術の確立に注力、04年に東証上場。15年に臨床事業を米国大手臨床CROのPPD社との合弁事業(新日本科学PPD)とし、グローバル臨床試験実施に注力しています。非臨床事業における米国からの受注高比率は4割ほどに伸びています。更に、社会的利益創出活動(新しい理論に基づく地熱発電、シラスウナギの人工種苗生産など)にも注力しており、鹿児島発のグローバル企業として、新薬開発になくてはならないダントツのCROを目指しています。

御社の現在の事業の強み・特徴やこれからの展望について教えてください。
製薬企業が重要視するのは、新薬開発の期間短縮です。当社は長年にわたり培った経験と実績をもとに、効率的な開発を提案できるCROを目指しています。特に非臨床試験受託における実験用NHP(Non-human Primate)の研究は、その規模・内容ともに世界的に高く評価されています。また、独自開発の経鼻製剤投与基盤技術を活用した医薬品開発を進めており、経鼻偏頭痛治療薬の新薬承認申請を米国FDAへ行いました。社会的利益創出事業の地熱発電では当社年間消費電力の約半分に相当する発電を行う一方、シラスウナギ人工種苗生産研究は大量生産の準備段階に入っています。女性活躍推進に優れた企業として、内閣総理大臣表彰など様々な賞や認定を獲得しています。

企業から見た地域の魅力について
御社から見た鹿児島地域の魅力について教えてください。
薩摩が輩出した明治維新の中心的人物、西郷隆盛は歴史書ではがんこな人柄のイメージと思いますが、鹿児島の人々は素直で誠実な気質を持ち、郷土愛に満ちて地域社会の発展に協力的であり、著名な人物を数多く輩出しています。有名な鹿児島の黒牛、黒豚のほかにも、新鮮な魚や野菜など、質の高い食材が安価で市場に出ており、経済的に安定した生活を送りやすい点が魅力です。航空路線や新幹線など、交通インフラが充実しており他地域へのアクセスが良好で、交通渋滞も少なく快適に運転できます。鹿児島を代表する桜島や霧島など、美しい景観も見逃せないポイントで、自然豊かな風景に囲まれて健康的に暮らせることは大きな魅力といえます。

企業が求める人材像について
御社に応募していただきたい人材像について、具体的に教えてください。
女性活躍を目指す企業として、皆が幸せに楽しく働ける会社の実現に向けて従業員の個性を尊重し、社員の生きがい・働きがいを向上させることで、社員一人ひとりの目標達成を応援しています。社内教育部門「SNBLアカデミー」を中核として、新入社員から管理職まで幅広い人材を育成する複数のプログラムを並行して展開しており、人財を育てる制度が充実しています。その中でも、社長自身が講師として教育する「永田塾」は今年で12期目となり、既に若手管理職が200名以上育っています。当社は、困難に挑戦し自己成長に注力し続ける人財、道徳的な判断ができる責任感の高い人財に応募していただきたいと期待しています。

ひとを知る
代表取締役会長兼社長
永田良一
1991年に株式会社新日本科学の代表取締役社長に就任後、1997年に代表取締役社長 兼 CEOに就任。そのほかにも、メディポリス国際陽子線治療センター 理事長(2006年〜)・駐日ブータン王国名誉総領事(2010年〜)・学校法人ヴェリタス学園 理事長(2010年〜)・学校法人順天堂 理事(2020年〜)・聖マリアンナ医科大学 理事(2020年〜)を兼任している。
SDGsへの取り組み
- 【3】患者様に早く新薬を届けるために時間価値を創出する新たな創薬エコシステムの改革に取り組んでいます。
- 【5】女性活躍企業として社内で組織横断的に改善チームを編成し、数々の受賞や認証を獲得しています。
- 【7】民間企業として国内で初めての地熱発電所を運営し、毎年約1,000万kWhを発電しています。
企業プロフィール
| 企業名 | 株式会社新日本科学 |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-1394 鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438 |
| 創業年 | 1957年創業 |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 永田良一 |
| 事業内容 |
|
| WEBサイト | リンクはこちらから |
| 求人応募ページ | 株式会社新日本科学 採用サイト株式会社新日本科学 新卒採用ページ株式会社新日本科学 中途採用ページ |
| 企業ロゴ |  |